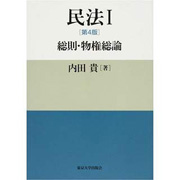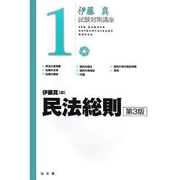第277号 2007・8・9
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法350条の解説です。
350条は、準用条文ですので、今までに解説していることばかりです。
すぐに理解できると思いますので、さらっといきましょう!!
それでは、さっそくはじめていきましょう!!
第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
■■ 解説 ■■
さて、冒頭でも紹介しましたが、この民法350条は準用条文です。
296条から300条までの留置権の規定、304条の先取特権の規定が準用されています。
では、なぜ留置権や先取特権の規定が、質権についても準用されているのでしょうか?
大きな視点を持っている方ならすぐにわかると思います。
なぜなら、留置権も先取特権も質権も全て担保物権だからです。
質権の条文ばかりを見ていると、自分が民法全体の中のどこにいるのかが分からなくなることがあります。
よく木を見て森を見ず!と言います。
森の中で迷わないためには、常に自分が森全体の中のどこにいるのかということを意識する必要があります。
目の前の木ばかりを見て進んでいると全体の中での自分の位置がわからなくなり、迷ってしまうのです。
これが法律の勉強にもそのままあてはまるのです。
目の前の質権の条文ばかりを見ていると、自分が民法という法律の中でどの部分を勉強しているのかが分からなくなって迷ってしますのです。
常に、一つ一つの条文を勉強しながら同時に、その条文は民法全体の中でどの部分の条文なのかということを意識して勉強しなければなりません。
今は、第2編物権編>担保物権>質権の条文を勉強しています。
留置権も先取特権も質権も担保物権ですので、かなり共通している部分が多いのです。
ですから、留置権や先取特権の条文が、質権にも準用されているのです。
準用されている条文についての詳しい解説は、既に解説しているものばかりですので、バックナンバーで確認しておいてくださいね。
簡単に準用されている条文を解説しておきます。
296条は、不可分性を規定している条文です。
297条は、果実からの優先弁受領権を規定している条文です。
298条は、留置権者の留置物保管義務を規定している条文です。
299条は、留置権者の費用償還請求権を規定。
300条は、被担保債権の消滅時効についての規定。
306条は、物上代位についての規定です。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
民法の全体をもう一度確認しておいてください。
六法を持っている方は、民法の目次を見ると全体を把握することができるのでおすすめです。
目次をコピーして、常に参照しながら勉強すると効率的です。
■■ 編集後記 ■■
今日は、特に解説することはありませんでした。
しかし、マクロな視点とミクロな視点を常に持って勉強するというのはほんとに大事ですので、ぜひやってみてください。
これは、法律の勉強に限らず、どんなことにも役に立つはずです。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
(裏編集後記)
受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。
今から、サーフィンに行ってきます。
初めてのサーフィンで、かなり楽しみです(^—^)
このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。
次の記事:>> 民法第351条(物上保証人の求償権)|毎日3分民法解説メルマガ
【YouTube】独学応援!行政書士塾
YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!
管理人の著書
【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!
メールマガジン登録
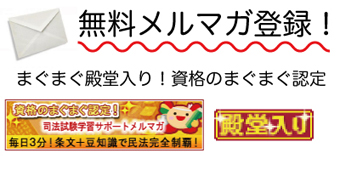
このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。